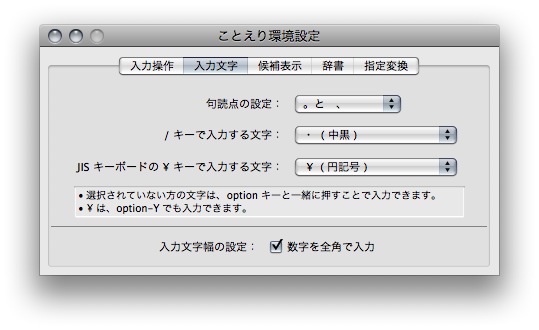2009 年 1 月 20 日
から Yo
0件のコメント
(2009/6/4追記)カホンを購入して、ちょっと考えが変わってきた。カホンは振動面が木なわけだが、モノによってはびっくりするくらいのローが出る。また、これを書いた当時は「ヘッドを外した状態のシェルを叩いても音はたいして出ない」ということを書いていたが、「ヘッドをピッと張った状態のドラムシェルが、振動を受けてどの程度発音するのか」を考えないと意味がない。
やはり大きくはないにせよ、多少影響はあるような気がしてきた。「シェルの振動が音に影響するタイプのタイコ」と、「シェルはほとんど振動せず、ヘッドの鳴りで音を作るタイプのタイコ」とに、大きく分かれるような気がしてきた。(2009/6/4追記終わり)
ドラムメーカーのカタログや某ドラム雑誌、教則ビデオなんかを見聞きしてると、良くこんな表現が出てくる。
- 「シェル(胴)鳴りが太く〜」
- 「薄胴シェルは良く振動するので音が〜」
あまりに頻繁に出てくるので、ドラムの胴は音に影響を与えるほど「鳴っている」というのが常識かのように感じてしまうけど…本当かなー?と。
冷静に考えてみると「音はほとんどヘッド(皮)からしか出て無いだろう」と思えてくる。ヘッドやパーツを全部外した「ただの筒」状態の胴をマレットで叩いてみたことがあるが、「ボン」程度の小さな音しか出ない。これはやってみなくても容易に想像がつくハズ。そんな胴が「ヘッドを張って叩くと、強烈に振動して(サウンドに影響するほどの)音を出す」とはどうしても思えず。
ヘッドの張り具合、打撃を受けた時の振動の仕方に胴も影響してるのは確かだろうし、胴自体も確実に共振するだろう。その振動がエッジを通してヘッドに伝わりもするだろう。実際に個々のスネアの音は違うので、「材質やつくりが違うと音が違う」のは事実だ。でも、「胴自体が発する音」はヘッドに比べれば無視できるレベルだと思うので、「胴鳴り」って表現はやはり違和感を感じる。
Webを検索してみると、同じことを理詰めで究明している方がいたり(*1)して、尊敬のまなざし。物理はスルーで来てしまった僕にはちょっと真似できない。←生物系理系
*1 深大寺しんぷるてくのろじー研究所の「ドラム研究室」です